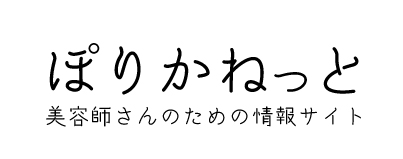今日は、日本の和装のことについて学んでいきましょう。かーくん、成人式にどうして振袖を着るか知っていますか?

いざそう考えてみると、検討もつかないですよね。女性は振袖にかんざし、綺麗な帯、というのが鉄板。では男性は?きっちり着こなした着物に、シックな色味の袴で、女性とは反対なイメージがあります。これらを紐解くきっかけとして、はじめに振袖の起源からみていきましょう!
”袖を振る”

本当に、そのままなんです。袖の長さは3尺、大体114センチくらいのものを振袖と言います。”振る”という行為には厄をはらい、縁を呼び寄せるという意味があり、この考えを応用したのが、振袖なのです。未婚女性が着用するものでもっとも格式高いものですから、婚姻を交わす前の縁起物として身につけていたのです。

逆に、既婚女性は袖を振る必要がないので、袖を切るのが慣例です。結婚したら留袖を着るようになるのもお忘れなく。
それでは次にいきましょう。男性の和装は結構種類がある印象ですが、実際は?みんな毎日袴を履いていたと思いますか?
男性の和装
江戸時代の男性は階級によって着る服が違っていました。例えば公家の男性は袈裟をまとい、武家の男性は普段着とお目見えする際の服は分けていたそうです。
こんな格好をした武士をみたことありませんか?


そんな彼らも、普段着は、こう。


こら、弱そうだなんて言わないで。よく目にする1枚めの画像は、武士の正装でした。階級関係なく、裃を着るのですが、長さで位がわかるようになっています。位が高い人は長裃、逆に低い人は半裃と言って足首までの長さの袴を着用していました。

うーん、位が高い感じではなさそうですね。でも普段着は一般人も武家も変わりません。子流しと言って、袴を着ない、緩い格好で過ごしていたようです。夏はより涼しい、浴衣も着ていたんですよ。
髪かざり
女性の髪飾りとして有名なのはかんざしですよね。今では華やかなイベントの時に使われることが多いですが、昔は厄除けとして使われていたんです。
かんざしの始まりは縄文時代にまでさかのぼります。”飾り”ではなく、髪を束ねるためだけの”道具”でした。かんざしの尖った先に呪力が宿ると信じられていたので、女性を守るための必須アイテムだったんですね。

安土桃山時代からと言われています。道具から”飾り”へと変わっていた時期ですね。髪の毛もまとめるから”結う”に変化しました。身分の高い人たちは、依然として髪の毛をおろしていましたが、商人たちは髪が長いと邪魔になりますので、かんざしを使っておしゃれを楽しんでいたんです。
かんざしが完全にファッションになったのは江戸時代になってから。花を象った花びらかんざしから、小さな布を花の形にしていくつまみかんざしが流行したのです。

色とりどりでつけるだけで華やかな気分になりますよね。
他にもこんなにたくさん種類があるんですよ。

これは平打ちかんざし。名前の通り飾りの部分が平べったくなっていて、とてもシンプルなものになっています。

これは玉かんざしです。平打ちかんざしのようにシンプルですが、玉の中に花や金箔などがちらばめられ、つけるだけで一気に華やかさが増します。現代のお祭りなんかでも使われることが多いようです。

続いてこちらはびらびらかんざしという名前の豪華なかんざし。通称ビラカンと呼ばれています。未婚女性や幼い女の子がつけるものとして、流行しました。歩くたびに飾りが揺れてとても愛らしいかんざしですね。

あら、他にもたくさんありますよ。むすびかんざしやバチ型かんざし、むすび細工や飾りぐしといった変わり種まで。

かーくんはまだまだですね。これからヘア以外にもたくさんのことを学ばないといけないですから、大変ですよ。さあ、次回も元気に、楽しく勉強していきましょうね!